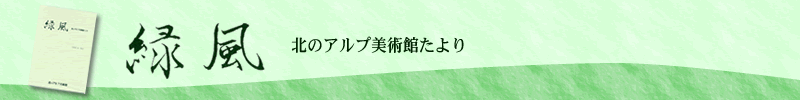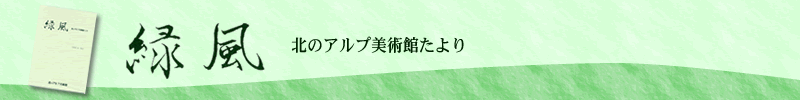|
雑誌と書籍の編集に携わって、早いものでもう40年にもなる。長かったようでもあり、あっという間の出来事だったような気もする。おいおい、過去を振り返るには、まだまだ早すぎるんじゃないの、という声も聞こえてくる。
そうしたこれまでの編集経験のなかで、『アルプ』という雑誌に関わりをもてたことは、とても感慨深いものがある。1958年の創刊であるから、私が実際の編集現場に入ってきたときには、すでに完成され 、地に足をつけた 雑誌の地歩を築いていた。その上質な随想や紀行、詩などの内容はもちろんのこと、余白を生かした体裁や広告を入れないその方針にいたるまで、ずっと気になるいわば憧れの存在だった。だから常連の執筆者たちと新たな接点をもち、原稿を依頼することも少なからずあった。 その代表的な 1 人が、山口耀久さんである。
どちらかというと、串田孫一さんをはじめとした東京外語大の 関係者 たちは、おしなべて紳士的である。一方、山口さんは、そのべらんめい口調からか、時に過激とも映る思考が対照的でさえあった。私が初めて、大森の高層アパートに山口さんを訪ねたのは、その『アルプ』 が終幕を閉じようとしていた ころだったと思う。依頼した原稿はあっさり断られてしまったが、下町ふうの口ぶりは健在で、ついつい話に惹きこまれてしまったことを覚えている。
爾来、機会をみては、久我山の「福寿荘 」という花好きの山口さんらしいアパートに何度となく足を運んだ。その折々、原稿の依頼はそっちのけで、豊富な話題に時間のたつのも忘れて話し込んでしまう。山口さんは意識していないかもしれないが、かつて編集者でもあった彼の口から編集や本作りの楽しさが語られるのである。そこには編集者の矜持もあったと思う。そしてその根底に流れていたのは、 決まっ て、学ぶ姿勢と人への興味、そして見る目の優しさだった。
 |
『山荘アルプ』で執筆中の山口耀久氏
2008年8月19日〜10月5日まで滞在 |
そうした時間の積み重ねがあったからこそ、山口さんの労作『「アルプ」の時代』は完成したと思う。本が店頭に並んだとき、多くの人から「大変だったでしょう」と言われたが、私はそう思ったことは1度もない。確かに書籍ができるまでに、これほどの時間がかかるとは思わなかった。しかし、それはすべて「醸造」するために必要な時間だったのではないだろうか。じっと待つことも重要な編集作業であることを、山口さんはまさに身をもって教えてくれたのである。
《元「山と溪谷」編集長》
|