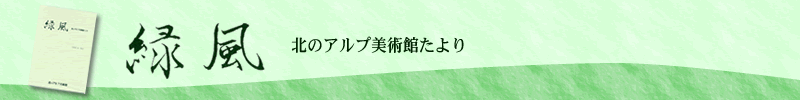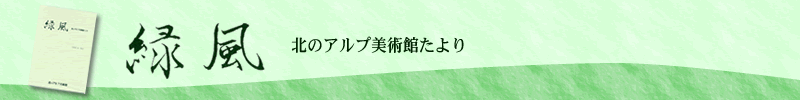|
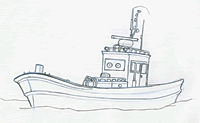 さい涯の番屋に 命の火ちろちろ さい涯の番屋に 命の火ちろちろ
トドの鳴く夜は いとし娘が瞼に
誰に語らん このさみしさ
ランプの灯影に 海鳴りばかり
「オホーツクの舟歌」というテープを知人が送ってくれた。これはその一節である。五十年も昔に作られた映画「地の涯に生きるもの」の長期ロケが終わったとき、森繁久弥が即興の歌詞と曲で歌ったものだという。これが後に「知床旅情」として加藤登紀子によって世に 膾炙(かいしゃ) されたことは、よく知られている。
戸川幸夫が映画の原作「オホーツク老人」を書いたのは、一九六〇年(昭35)以前だから、ずいぶん早くに知床半島を調査取材していたことに驚嘆する。
戸川幸夫さんにお会いしたとき、当時の苦労を問うと「先駆者の努力は忘れられて行くものですね」と、つぶやかれたことが忘れられない。
私が知床を知るようになったのは、初めて羅臼岳に登った一九六〇年ころが始まりだった。その後網走に住まいし、知床半島のオホーツク老人(番屋守)を訪ねるようになったのは、一九七〇年(昭45)前後だから、映画が作られてから十年も後になる。
すでにオホーツク老人は消えて行こうとしていた。番屋守は高齢化し、漁業の形態が変化しはじめて、かつての番屋守たちはウトロ市街にひっそり暮らしたり、 網走市 で余生を送っている状況だった。網走湖を望む養護施設で出会った老人は、「あれはわしの話さ。わしがモデルなんだ」と言った。小柄だったが、「地の涯に生きるもの」の主人公彦市老人を彷彿させる雰囲気があった。モデルの真偽はともかく、まだ番屋守経験者が生きている時代だった。
知床半島を一望にする海に面した高台に暮らす私は、とうにオホーツク老人を超える年齢になっている。そのせいか、「さい涯の番屋に命の火ちろちろ」という詞がしみじみと胸にしみる。
番屋でのひとり越冬のさみしさを問うと、ある老人は「何もさみしくないさ。流氷が押し寄せる音のする晩は、酒を一杯多く飲んで寝るのさ」と語っていた。「誰に語らんこのさみしさ」は、私が想像するより深いものがあったのだ。
そんな古い時代の知床の思い出を反芻する日々である。進歩と変化は止む得ないとしても、世界遺産後の知床は、前のめりになって急いでいるように見える。何百年という時間の中で、知床は人間も動物も自然も、命の火をちろちろと燃やし続けて来たのではないか。観光などという短いスパンで考える大地ではない。ゆったりとした時間の中で、変貌していく知床の未来を考えていきたい。
《文筆家・「流氷の見える丘から」著者》
|